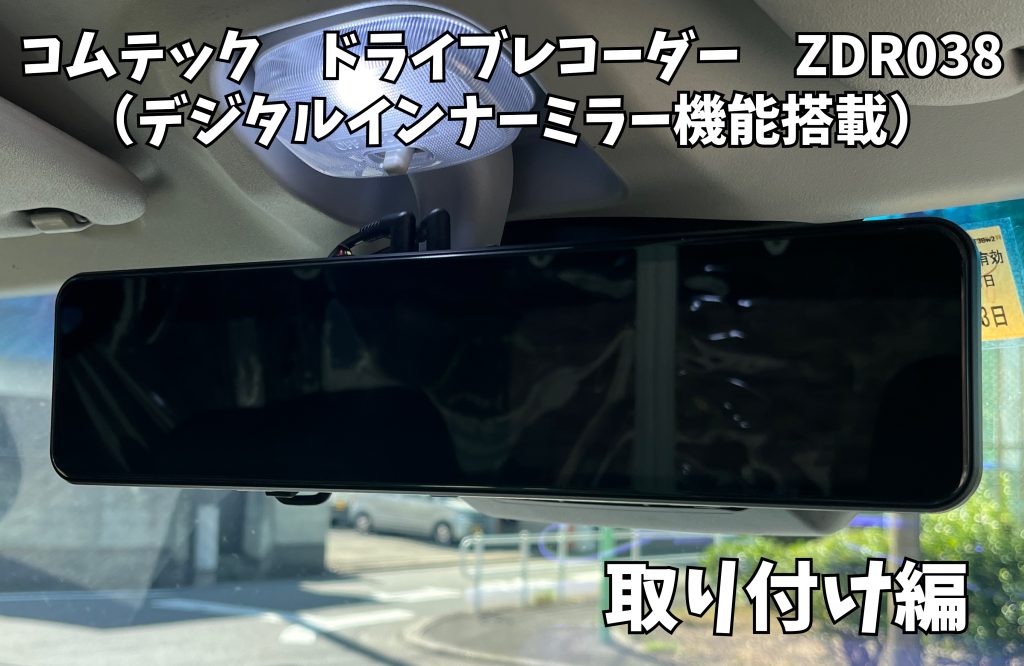Masaさん
最近、軽貨物が関わる事故が多くなってるみたいですね。
なんとか事故が減って欲しいものですね。
Mihoさん
そうですね。
コロナからEC取引が急激に増えて配達ドライバーが足りてない所もかなりあるみたいです。
それが原因で疲労や注意散漫からくる事故が増えているみたいです。
こういった事故を減らすために、国が軽貨物事業者に対して安全対策の強化を行うようなので
それについて、解説していきますね。
今回対象になる事業者は?

2輪の対象者は?
2輪(3輪含む)で対象になる事業者は、
事業用の125cc超の2輪車や既定サイズを超えた50cc超のトライクを使用している事業者が対象です。
(ひらたく言うと、緑ナンバーの軽二輪・小型二輪を使用する事業者が対象です)
125cc以下の第一種・第二種の原動機付自転車は対象外です。

4輪の対象者は?
4輪で対象になる事業者は、
事業用の軽貨物車・事業用の軽乗用車で「貨物軽自動車運送事業の用に供するもの」を使用している事業者が対象です。
(ひらたく言うと、黒ナンバーの軽自動車で、荷物を運ぶ用途で登録された車両を使用する事業者が対象です。)
事業用の軽乗用車でも旅客輸送に供するもの(介護タクシーなど)は対象外です。
通販の宅配をやっていないから不要・軽乗用車だから不要と言うことではありませんので、注意してください。
フードデリバリーやネットスーパーなどであっても、該当する車両を使っている場合は対象者になります。
軽貨物・自動二輪で宅配をしていても該当しない人は?
大手宅配やAmazonDSPなどに所属し委託会社から車両を借りている(リースしている)場合で、車両の使用者名義が自分になっていないものの場合は原則該当しません。ただし、委託会社から安全対策の強化に対応するために必要な項目の実施を求められる場合があります。その場合は委託会社からの指示に従う必要があります。
リースの場合でも、信販会社やカーディーラーのリースで車両の使用者名義が自分いなっているものは今回の安全対策強化の対象となります。
該当者がわかったところで、ここから先は、実際に強化される内容のお話です。
①貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

配送拠点ごとに貨物軽自動車安全管理者の選任・届出が必須となります。
選任とはいっても多くの方は1人でやっている場合がほとんどだと思いますので、ご自身を選任する形になります。
貨物軽自動車安全管理者は選任日時点で過去2年以内に
「貨物軽自動車安全管理者講習」か
「貨物軽自動車安全管理者定期講習」を受講している必要があります。
届出は受講終了を証明する証明書を添付して各都道府県の運輸支局へ
届出書のサンプルはこちら
猶予・免除は?
2025年3月31日までに事業を開始している事業者は2027年3月31日まで2年間の猶予期間があります。
2025年4月1日以降に事業を開始する事業者に対する猶予期間はありません
使用している車両が二輪(緑ナンバー)のみの場合はこの項目は免除されます。
②貨物軽自動車安全管理者(定期)講習の受講

貨物軽自動車安全管理者に選任されるには貨物軽自動車安全管理者講習の受講が必要となります。
また、選任中(事業継続中)は2年ごとに貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講が必要になります。
猶予・免除は?
選任・届出までの期間に猶予がある事業者に該当する場合は実質的に猶予期間があると考えられます。4月1日以降に事業を開始する方の場合は選任・届出に猶予期間がありませんので猶予がないと言う事になります。
また、使用している車両が二輪(緑ナンバー)のみの場合はこの項目は免除されます。
③初任運転者等への指導及び適正診断の受診
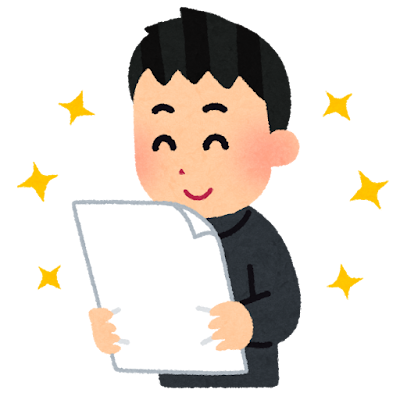
以下に該当するドライバーに適正診断の受診・特別な指導が必要です。
また、受診・指導記録を保管する必要があります
適正診断の対象者は
①初任運転者(初任診断)
②65歳以上(適齢診断)
③死傷者が発生した事故をしたドライバー(特定診断)
初任運転者は過去に適正診断と特別な指導を受けたことがない64歳以下の人が対象です。過去に業務経験があっても初任診断の対象者となります。
また、過去にドライバー職などで受けたことがある場合でも、受診記録が残っていない場合には再受診が必要となります。
初任運転者が65歳以上の場合は適齢診断を受診する事によって、初任診断を省略することができます。
初任診断を受けた人が65歳以上になった場合、適齢診断の受診をする必要があります。
特別な指導とは?
5時間以上の時間を使って
①貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項
②事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項
について指導をすることとされています。
安全運転の実技(添乗指導)についても可能な限り実施することが求められます。
乗務開始前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受講することでも特別な指導を受けたとみなすことができます。
猶予・免除は?
2025年3月31日までに事業を開始している事業者は2028年3月31日まで3年間の猶予期間があります。
2025年4月1日以降に事業を開始する事業者に対する猶予期間はありません
使用している車両が二輪(緑ナンバー)のみの場合はこの項目は免除されます。
④事故の記録

業務中の事故が発生した場合は以下の事項を記録し3年間保存しなければいけません
①事故時の運転者・同乗者等の氏名
②事故の発生日時
③事故の発生場所
④どのような事故であったか
⑤事故の原因
⑥再発防止策
猶予・免除は?
2輪・4輪ともに猶予期間・免除規定はありません
2025年4月以降に発生した事故については全て記録を残す必要があります。
業務時間外に起きた事故については記録不要
⑤国土交通大臣への事故報告
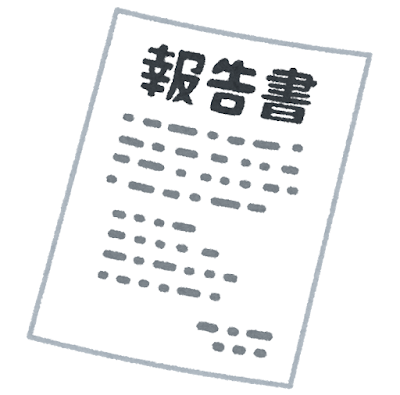
④の「事故の記録」の中で特に重大な事故が発生した場合は30日以内に所定の様式で運輸支局などを通じて国土交通大臣に報告する義務があります。
①自動車の使用者の氏名・名称
②事故の発生日時
③事故の発生場所
④どのような状況であったか
⑤どのような処置をしたか
⑥事故の原因
⑦再発防止策
猶予・免除は?
2輪・4輪ともに猶予期間・免除規定はありません
2025年4月以降に発生した事故については報告義務が発生します。
業務時間外に起きた事故については報告義務はありません
⑥業務の記録
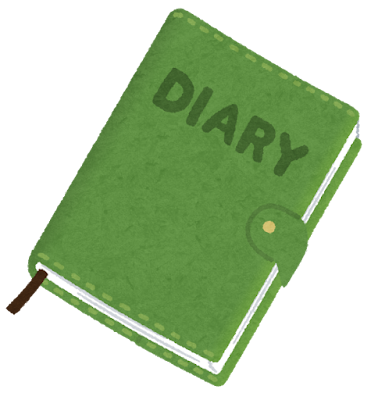
業務の記録は1年間保存しなければいけません。
記録が必要な項目は以下の6つです。
①運転者の氏名
②車両番号(ナンバー)
③業務の開始・終了・休憩時間の日時
④業務の開始・終了・休憩の場所
⑤走行距離
⑥主要な通過地点・集配エリアなど
猶予・免除は?
2輪は記録が免除されています。
4輪は2025年4月以降に従事した業務について記録を残す必要があります。
おそらく、多くの人にネックになるであろう「業務の記録」
今までは業務の記録の保管義務がなかったので、勤務時間についておろそかになっていた人が多いのではないでしょうか?
業務記録の保管が必須になったことで勤務時間・運転時間について過去を遡って記録を確認できるようになります。
記録が無かったことで有事の際などに責任追及される可能性もありますので、気をつけて運行計画を作る必要があります。
時間の規定についておさらい
①連続運転時間 4時間以内
4時間ごとに30分以上の休憩を取る必要があります。(集配業務など短時間の運転離脱は運転中とみなされます)
②1日の拘束時間 1日13時間以内(上限15時間以内)
13時間超は週に2回までを目安とする
(拘束時間は労働時間と休憩時間を足したもの、労働時間には待機時間を含める)
③1日の休息時間 原則11時間以上のリードタイムを設ける
やむを得ない場合は9時間以上でも可
④連続運転時間
前後2日間の平均9時間以内(2日間で18時間まで)
前後2週間の平均44時間以内(2週間で88時間まで)
⑤1ヶ月の拘束時間 284時間まで
⑥1年の拘束時間 3300時間まで
罰則規定は?
罰金刑や、期間を定めた業務停止命令などがあります。
最悪の場合は取り消し命令になる場合もありますので、十分注意していきましょう